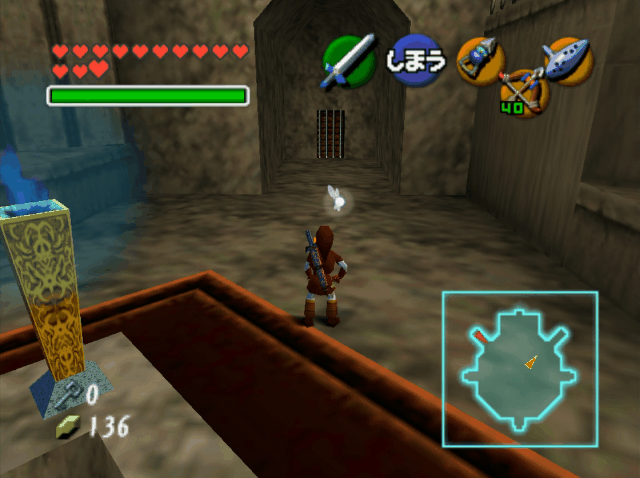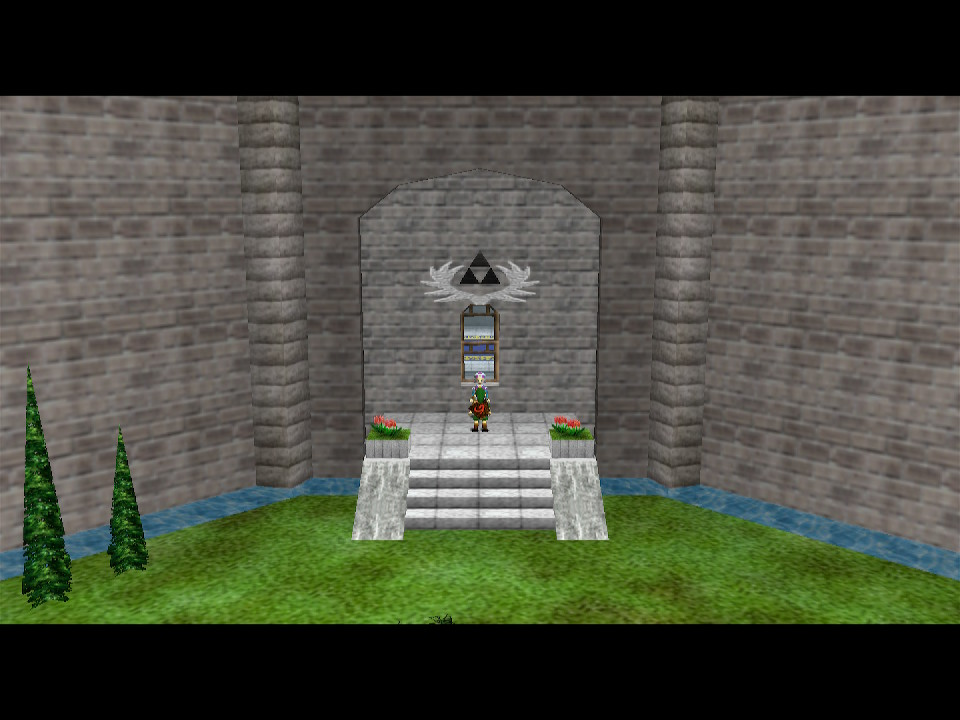その冒険は、英雄譚として刻まれる
Dragon's Dogma Ⅱ(以下、DD2)はCAPCOM より販売されたオープンワールド 型のRPG タイトルだ。モンスターハンター などのRPG 的要素が含まれるタイトルも存在するが、本格的なRPG タイトルは主戦場ではないだろう。オープンワールド に挑戦した作品でもあり、その作品がナンバリングタイトルとして帰ってくるのは嬉しい限りだ。
ストーリー
物語としての説得力は微妙だがライフシム世界としては魅力的だ
ヴェルムントという地域のメルヴェ村にてドラゴンに襲われて心臓を奪われる。そうして主人公は「覚者」という存在になった。空位 時代を過ごす中で利権争いが起きるようになってしまい、その中で公妃派による手引きにより偽の覚者王が擁立されてしまう。
本作冒頭のチュートリアル デザインも丁寧に作られている。ラク ターを選択あるいは作成するシーンもストーリーの延長として機能するようになっているのも良くできていているが、冒頭は牢獄から開始するため行動が制限されておりチュートリアル として機能させやすいシチュエーションにもなっているのだ。
前作と同様にストーリーとしてもゲームプレイとしても特徴的なのは「従者ポーン」という存在となる。NPC が随伴する形で物語を進行していく事になるのが基本だ。エス トなどの様々なシチュエーションでヒントなどを喋りかけてくれるようになっている。RPG でありながら、仲間と一緒に冒険してる感を味わいながらプレイできるように作られているのがストーリー進行における本作独自の色合いだ。
本作で特に知っておくべき内容についても記載したい。ジー 世界ライフシム」のような志向性が強いという点だ。ジー 世界での生活感ある冒険」という側面を体験したいのであれば期待に応えてくれるだろう。
ストーリー自体にももう少し触れたいが、メインとなるストーリーは説得力や納得感がやや欠けている。エス トがそこらの傭兵や間者が受け持つような内容の危険なものになっているのだ。
サブクエス トは豊富になったがNPC のリアクションは物足りない
本作では多くのネームドNPC が登場する。NPC のサブクエス トが非常に充実しているうえにNPC の存在感を示すためのNPC 図鑑も用意されている。エス トが別のサブクエス トと関連しているケースもあるなどの関連性が構築されているため充実したコンテンツになっている。オープンワールド と言う環境を活かせる偶然性に重きを置いたデザインも見受けられる。
そこまでは良く出来ているのだが、広範なNPC のデザインは物足りなさが強い。エス ト外でのNPC の対応が機械的 であるためだ。エス トの時には色々と経緯や思いを喋ってくれるのだが、ひとたびクエス トが終わってしまうと同じセリフを喋るだけのマシーンと化してしまう。機械的 に感じる要因と言っても良いだろう。NPC に話しかける事ができるようにしているにも関わらず、誰に話しかけても大したセリフを喋ってくれない事も同様だ。ドレスコード でなければならない場所があるのだが、しっかりと基準を満たしているのに注意をするセリフが発せられプレイヤーを困惑させてしまうといったケースも存在する。NPC はとにかく物量が多くなってしまう事から作り込むのは大変なのは理解できるが、世界の生活感にも直結する要素でもあるためもう少し配慮して欲しかった部分だ。
システム
ここではゲームプレイに関わる要素について記載する。
キャラク タービルド
様々な個性を持ったジョブによって立ち回りが大きく異なる
プレイヤーキャラク ターと仲間NPC 従者ポーン(メインポーン)を一人ずつ作成、ビルドしてゲームプレイを行っていく事になる。ラク タークリエイトは単純な外見という意味合いに留めず、身長などの体格によって最大積載重量も変化するような仕組みになっている。ラク ター作成方法によって不公平さが生まれてしまうゲームとしては問題ある仕組みだが、それは本作がファンタジー 世界ライフシムとしての側面を強調しているがためにあえて採用しているものとなっている。
作ったキャラク ターにはジョブが設定される。ラク ターの戦闘における役割を設定する項目だ。ティー 編成を考えるのがベターだろう。
プレイヤー自身にもレベルの概念があるが、ジョブにも熟練度の概念が存在する。
もちろん、キャラク タービルドには装備類も含まれる。ラク ターのご尊顔を拝めなくなってしまう。ユーザビリティ ーよりもライフシム的な側面に準拠したデザインになっており、不便さはあるものの性能と見た目の両立をプレイヤーが工夫する楽しさでもある。
戦闘
非常に軽快で相変わらずユニークなアクションが強化されている
DD2はCAPCOM らしい制御性に優れたアクションによるモンスター攻略に重きを置いた戦闘が楽しめるのは大きなポジティブポイントだ。
HPは前作と同じ仕様で被ダメージによってHPとは別に最大HPも削られる。
プレイヤーの攻撃手段は剣などによる近接攻撃の他にも弓や魔法による遠距離攻撃も存在する。攻撃機 会が減少する事に繋がってしまう。ティー 全体のDPSが落ちてしまうため結果としては効率的とは言えないが、プレイヤーの工夫次第で敵を手玉に取るようなゲームプレイができる非常に珍しい個性的な体験ができるだろう。
戦闘において気になる点があるとすればザコ敵のバリエーションの少なさだ。
困った挙動も散見される
敵の攻撃は困った挙動も見受けられる。ラク ターがいる事も確認できるだろう。リスク管理 を行うことは難しく、プレイヤーの行動を萎縮させかねない。
ポーン
攻略を強力に手助けしてくれる仲間NPC ポーンが主軸だ
DD2のメインコンテンツと言えるのが従者である「ポーン」だ。NPC で、自律的に行動してモンスターに攻撃したり、回復を行ったりしてくれるような存在である。NPC の域を脱しているのは「ポーンは他プレイヤーの世界で経験を積み、そこで得た情報をプレイヤーにフィードバックできる」という点である。エス トをクリアする事で経験を積んでいく事が出来る。
もちろんポーンは自身がクリエイトするメインポーンも同様の事が可能だ。エス トの攻略情報を蓄積して、他プレイヤーの攻略の手助けになるほか、他プレイヤーが自分のポーンを雇った際に行った行動によって攻略情報を逆輸入してくれるような事もある。NPC が攻略の援助と言う形でフィードバックしてくれるのはユニークだ。
このポーンは最大で2名雇う事が可能で、自身のメインポーンも含めて4人パーティー になる。ティー のバランスを考慮して雇うべきだろう。
メインコンテンツでもあるポーンだが、このポーンには問題ある仕組みも導入されている。NPC を大量殺害に至ってしまう事になると言う。NPC は希少な専用アイテムを用いる事で復活させることが可能だが、プレイヤーにそういった手間を強いる事になる。
フィールド
フィールドは完全なシームレスに
DD2のフィールドは完全なシームレスなオープンワールド になっている。ジー 世界ライフシム」としてプレイして欲しいという意図が汲み取れるものとなっている。
フィールド上にはモンスターが跋扈しているが、そのモンスターが市街に迷い込んで暴れまわるような事もある。NPC が死亡してしまう可能性もある。
フィールドはシームレスなだけではなく広さに関しても前作よりも広くなったが、ライフシム的な側面を強調したためか移動に関しては前作よりも不便になっている。
しかし、ここまでの話だけでは問題であると言えるものではない。NPC であるポーンに荷物を預けてパーティー 全体で負荷分散を行えばある程度の重量には耐えられるが、ポーンに所持している荷物を渡す際に複数選択が行えないうえなどの制限や手間が多い。
移動とは多くのゲームにおいて必ず必要な行為であり、重量制限にしても、ポーンを活用した負荷分散にしても「旅情」という本作の一貫したライフシムの側面だ。
モンスター同士が争っている事も
ライフシムとしてのファンタジー 世界を表現しているDD2の世界ではモンスター同士が争っている事もある。
キャンプは旅を演出するが、もう少し作り込みが欲しい
既に簡単には記述しているが、フィールド上では野営でキャンプをして休憩する事ができる。「夜」 といっても視認性はある程度はあるものだが、本作の場合には夜は本当に暗い。
「戦闘」の項で述べた通り前作では最大HPを回復アイテムで回復可能だったが、本作では最大HPを回復するには宿屋かキャンプで休憩する必要がある。
キャンプは本作のコンセプトである旅情を強く感じさせる要素として機能するが、もう少し作り込みが欲しいと感じるものでもある。
グラフィック
美麗に描写された自然と人々
フィールドは草原から森林地帯、荒地の岩山などいくつかのシチュエーションを用意している。
キャラク ターのアニメーションに関しても細かく作り込まれている。
映像面で気になるのはNPC が描画されるのが、プレイヤーが近くを通った時である事だ。NPC が非常に多い場所では30FPSを明確に切ったような瞬間がたまにあり、近くに行かなければ描画しないようにしているために安定性が実現できているのだろう。NPC がヌッっと表示されるのは違和感に繋がる。
痒い所に手が届かないがフォトモ ードがある
やや簡易的だがフォトモ ードも存在する。スクリーンショット は難しい。
実写映像を使うという荒業
キャンプでは肉を焼くなどの料理が行えるが、なんと実写が使用されている。ティー ルの凝った料理という訳ではないワイルドなリブを焼くだけのシーンを実写映像にしている。
大型モンスターとの戦いでは形成有利になるとBGMが変化するなどの大型タイトルには採用例が多いインタラクティブ ミュージックが主体である。
一緒に行動するのが基本となるポーンのボイスパタ ーンは前作よりは多くなっているが
総評
Dragon's Dogma Ⅱはファンタジー 世界で旅と冒険をするライフシムを全体を通して一貫して、そしてストレートに表現したRPG だ。
しかし、プレイヤーに体験して欲しい「ファンタジー 世界ライフシム」という内容に余りにも愚直にアプローチした結果として不便さが際立ってしまっている。ユーザビリティ ーを高める折衷案をもう少し検討しても良かったように感じられる。
口を開けばネガティブな部分ばかりを取り上げたくなってしまう本作だが、それでも全体を通してみれば非常に良くできた面白いゲームである事も事実として忘れてはならない。
外部記事
『ドラゴンズドグマ 2』インタビュー。ポーンのコンセプトは“親の顔が見たい”。前作のプレイ感を踏襲しつつ覚者とポーンの冒険はグッと厚みが増した【TGS2023】 | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com
[TGS2023]ファンタジー世界のシミュレータを目指して――「ドラゴンズドグマ 2」開発者インタビュー
[インタビュー]「ドラゴンズドグマ 2」が目指すのは,プレイヤーごとに体験が異なる「人に話したくなるゲーム」
『ドラゴンズドグマ 2』ではポーンが“嘘レンタル”されるとの報告。“偽プレイヤー”に借りられ、異界から帰還するポーンたち - AUTOMATON
実在しているかのようなファンタジー世界をゲームで表現したい 『ドラゴンズドグマ 2』開発者インタビュー
進化したAIや新要素「キャンプ」など『ドラゴンズドグマ 2』ディレクターインタビュー
【独占】『ドラゴンズドグマ 2』ディレクターインタビュー! 目指したのは、NPCと三角関係になれるほどに徹底的に作り込まれた異世界転生シミュレーター
開発者インタビュー:『ドラゴンズドグマ 2』の濃密な世界は、「冒険の価値」とは何かを追求して生まれた
『ドラゴンズドグマ 2』開発者インタビュー:スフィンクスへの拘り - YouTube
『ドラゴンズドグマ 2』キャラクリインタビュー:スキルに依らない理想の造形を実現できることを第一に - YouTube
『ドラゴンズドグマ 2』開発者インタビュー:“友達”に進化したポーンシステム - YouTube
『ドラゴンズドグマ 2』ディレクターインタビュー:制作裏に込められた伊津野英昭のこだわり - YouTube
『ドラゴンズドグマ 2』クリエイターインタビュー:世界観構築の裏側 - YouTube
『ドラゴンズドグマ 2』伊津野D&平林Pインタビュー。一歩歩けば何かが起こる、絶対に退屈させないオープンワールドは“前作の不完全燃焼”から生まれた - AUTOMATON
『ドラゴンズドグマ 2』インタビュー:「ポーン」の開発エピソードを聞いてきた
『ドラゴンズドグマ 2』インタビュー。ストーリーの自由度やジョブの種類、オンライン要素はどうなる? - 電撃オンライン
「ドラゴンズドグマ 2」インプレッション&インタビュー - GAME Watch