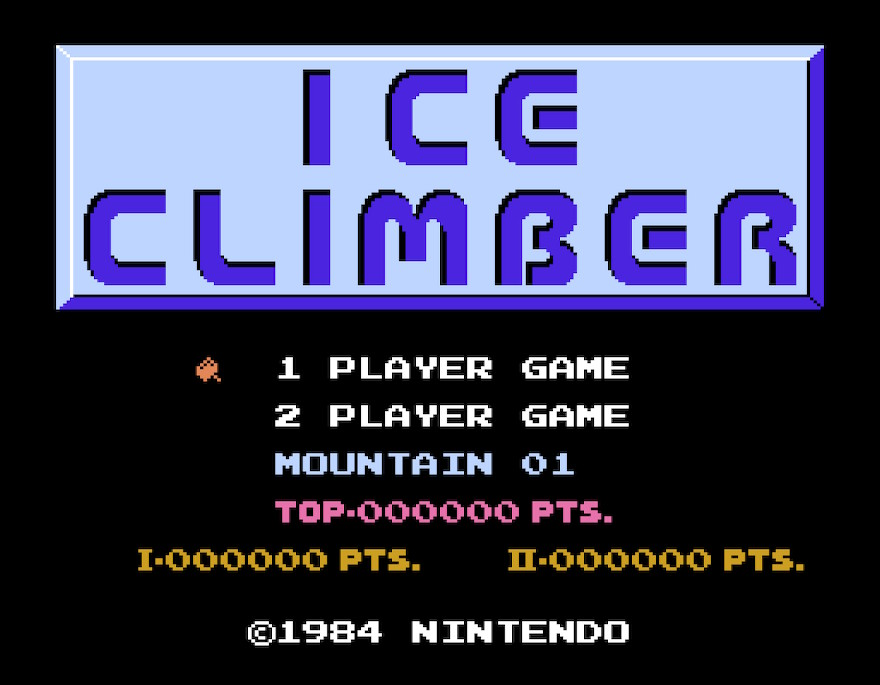
アイスクライマーはファミリーコンピュータにて発売されたジャンプアクションをベースとした作品だ。
本作は今回レビュー対象とするコンソール版の他にアーケード版も存在している。
この頃のゲームではアーケード版を後に家庭用コンソール向けに移植するという流れが一般的であるが、本作の場合には両者がほぼ同時期にリリースされているという少し特異な作品でもある。
また元々名作ではあったものの、後には大乱闘スマッシュブラザーズDXにてプレイアブルキャラクターとして登場した事で再び再認知された点も記憶にあるイベントだ。
なお、今回はNintendo Switch Onlineのファミリーコンピュータにて配信されたものを利用してスクリーンショットの撮影やレビューを行っている。
ストーリー

本作ではエスキモーの男の子ポポと女の子ナナが氷山の頂上を目指していくようなものである。
しかし、当時の作品では当たり前であったが、明確なストーリーがないため何故このような状況で、このような行為をしているのかはイマイチわからない。
あくまでもゲームプレイが中心となっており、遊び場のための言い訳のような説明を省いているのは現代では逆に珍しい潔さがあるといって良いだろう。
これは本作はアーケード版も同時期にリリースされている経緯があり、アーケード環境には「コインを入れたら即座に遊べる」などの「サクッと遊べて、サクッとやられる」という性質が求められる。
そういった点からストーリー要素自体が冗長になってしまうのだ。
こういったコンソール市場においてもアーケード文化・文脈が根強い点において日本のコンソールゲーム黎明期の背景を感じさせるものと考えても良いだろう。
システム
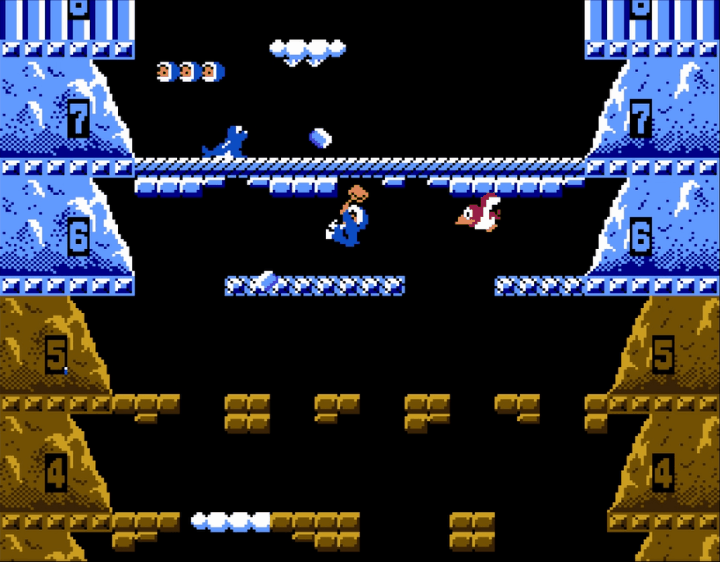
アイスクライマーは縦スクロール式のプラットフォーマーだ。
同社では先駆的にマルチプレイで楽しむマリオブラザーズ(1983年)が登場済みであり、本作はそれを拡張したような作品だと捉えても間違いではないだろう。
ルールとしてはジャンプを駆使して山頂を目指し、8階層目まで到達できれば暫定的なステージクリアとなる。
8層目以降はボーナスエリアで山の上を飛んでいるコンドルに触れる事が出来ればよりハイスコアを得る事ができるような仕組みである。
上へと昇る縦スクロールであるため、8層目以前に逆に下に落ちて画面外にまで行ってしまうとミスとなる。8層目以降のボーナスエリアでは下に落ちてもスコアが稼げないだけで次のステージへと進むこととなる。
これらの基本ルールを理解してクリアを目指し、ひいてはハイスコアを目指していくのが基本のゲームプレイとなる。
当時としては最後にはスコアアタックになる事は当たり前であったが、現代からするとエンドコンテンツとしては少しやりがいは落ちてしまうかも知れない。
山頂へと行くには上層の土台をジャンプによる頭突きで壊し、抜けた床からジャンプで通り抜けていく事が必要だ。
ジャンプは空中制御こそ行えるものの、かなり僅かな範囲であり距離を伸ばすにはジャンプするまでの助走が大切となる。
また、上層に上る際には見た目以上に余裕を持って着地できる位置でないとすり抜けるように落ちてしまうシビアさがある。
横着をするとかえって問題が起きやすく、まさにプラットフォーマーといったゲーム内容となっている。
ジャンプして上層に乗り移っても安心はまだできない。
床には種類があり、乗ると勝手に移動し続けてしまうものもあり、安全に上層に登れないようにもなっている。
山中には敵も配置されており、抜けた床を修復するような敵がいる事によってプレイヤーが早急に上層へ移動する事を促しているほか、時間をかけ過ぎてしまうと強制的にスクロールさせてミスにしてくるような敵がポップするなど、プレイヤーに進行を促す機能が採用された敵がしっかりと用意されている。
なお、一部を除けば敵に関しては手に持っている木槌によって退ける事が可能なので危ない場合には攻撃も必要となる。

アイスクライマーと言えばマルチプレイだと言っても過言ではないだろう。
大まかなルールはシングルプレイ時と同様だが、それを二人同時にプレイできるものである。
本作のマルチプレイは独特で、協力プレイのようでもありながら対戦プレイのようでもあり、どう立ち回るかがプレイヤーの選択に委ねられたファジーなマルチプレイ体験となっている。
例えば、山頂を目指す場合には上の階層の床を壊して、下層からジャンプで乗り移れるようにする必要がある。
この動き自体はシングルプレイと同様なのだが、マルチとなると「下層から上層にいる相手の足場を壊す」のと「一緒に上層へと移動できるルートを開拓する」という二重の意味合いを持つ行為が可能となる。
この「時として協力し、時として蹴落とし合う」というゲームプレイがユニークでファジーなマルチプレイ体験になっているのだ。
グラフィック


宮本茂作品、ひいては任天堂作品に多いが、本作も映像だけでプレイヤーがどのようなゲームプレイをすれば良いのか大まかにわかるように作られている。
例えば、最初はプレイヤーキャラクターが最下層にいる状態で、上層に大きな空間がある状態から開始される。
この視線誘導によってプレイヤーが上へと移動する事を促しているのである。
今でもお手本とも成りえるデザインと機能性をミックスさせた見事なレベルデザインである。
氷山を登っていくというゲームながら、道中にはナスやニンジン、カボチャなどが配置されていたりと少し不思議な世界である。
こういったミスマッチが内包された不思議さは本作固有のものではなく、当時のビデオゲーム文化全般に言える事である。
馴染みのない環境に、馴染みのある要素を取り込むのは多い手法であった。
サウンド
アイスクライマーではポップなBGMが印象的だ。
当時としては当たり前だが曲のループまでも短く、楽曲数も非常に少ない。
確かにその情報だけならチープであるようにも感じるが、プレイ中にずっと同じフレーズを聴くことになるため単純接触効果によってかなり耳に残るだろう。
総評
アイスクライマーはポップな見た目に反して非常に硬派なプラットフォーマーだ。
また、独特なファジーなマルチプレイ体験もかなり印象に残る作品である。
内容がシンプルかつワンコンセプトで構成されているため現代的な感覚ではボリュームやリッチさに欠けるところはあるが、今の時代に遊んでも十分な手応えが感じられる遊びの仕組みと操作感、そしてバランスになっているのは見事だ。
外部記事

