
ゼルダの伝説 知恵のかりものは2Dゼルダの完全新作となっている。
本作はゼルダシリーズの中でも待望の「ゼルダ姫が主人公のゼルダの伝説」という意味でも嬉しさがあった事を記憶している。
発表当初からそのビジュアルから制作はグレッゾではないかと思っていたが、発売が近くなった段階で正式に開発がグレッゾである事が発表された。
グレッゾと言えば聖剣伝説シリーズの生みの親である石井浩一氏の率いるデベロッパーであり、3DSのローンチタイトルとしてゼルダの伝説 時のオカリナ3Dを制作したところからゼルダシリーズとの縁のあるメーカーだ。
そんなグレッゾがシリーズのリメイク/リマスターではない完全新作の2Dゼルダを制作するという事で嬉しさがあった事を覚えている。
また、初報のトレーラーを観ただけでもゼルダの伝説 Breath of the Wildの路線を2Dゼルダで実現させたようなゲームプレイが印象的で、それだけである程度の面白さが期待できるようなものになっていた。
ストーリー

魔王ガノンに捕らえらえれていたゼルダ姫であったがリンクが救出に成功こそするものの、ガノンによる最後の一撃によって空間に亀裂が発生してリンクが取り込まれてしまう。
間一髪のところをゼルダ姫だけが逃げ延びる事には成功したが、世界の各地でも同様の現象が発生していた。
その亀裂は人を飲み込むだけでなく、魔物も出現するようになるなどハイラル王国全体の危機的な問題になっているようだ。
そんな中で王国へと逃げる事に成功したゼルダ姫の目の前でハイラル王を始めとする側近が亀裂へと飲み込まれ、ゼルダ姫は亀裂発生の原因と讒言されて牢へと入れられてしまう。
妖精トリィの力を借りて牢を脱し、ハイラルの大地を元の姿へと戻し、リンクやハイラル王、そしてハイラル王国を取り戻すゼルダ姫の冒険が本作の物語となる。
各地で発生している亀裂を発端として様々な問題が起きているため、その土地で生活している人と協力して解決するような物語となっている。
そのため、ゼルダ姫自身の成長が描かれると言うよりは各地のキャラクター達の変化や成長をベースとした物語になっており、これ自体はゼルダシリーズに多い物語構造と言えるだろう。
マップにはストーリーの目的地(クエストマーカー)が表示されるものの、必ずしも表示されたポイントに行けばストーリーが進行する訳ではない。
目的地では「南の○○で問題が起きてるみたいなんだ」という情報を聴くことができ、更に近隣の別NPCからも情報が得られたりするようになっており、ある程度は能動的に情報収集をしてストーリーを進める必要がある。
そうは言っても進行が難しく感じるほど難解な内容ではないので、しっかりとNPCとの会話を聞いていれば問題になる事はないだろう。
システム

基本はトップビュー形式のいわゆる2Dゼルダだ。
直接戦う手段が限られたゼルダ姫を操作して、フィールドにあるオブジェクトやモンスターを自由に出現させる事で攻略を行っていくと言うゲームスタイルとなっている。
最初期のチュートリアルを抜ければ攻略・探索順は完全に自由であり、本作のシステムを駆使すればどのような地域も序盤から到達可能なように作られている。
本作の特徴的かつゲームプレイの中心となる仕組みとして「カリモノ」と呼称されるオブジェクトを自由に出現させる事が可能な点だ。
カリモノはコスト上限に達するまで出現させる事が可能なうえ、上限に達したとしても再召喚すれば問題なく新品状態に戻る。
実質的にノーリスクでオブジェクトを召喚可能であり、このオブジェクトを活用してダンジョンや敵モンスターを含めて様々な方向性での攻略が行えるように作られている。
初期状態の上限は3コストまでであり、例えば1コストのオブジェクトは3つ召喚できるが、3コストのものは1つだけ召喚できると言った仕組みとなっている。
召喚可能なコスト上限を増やすためにはフィールドに点在するダンジョンを攻略する必要がある。
ダンジョンはストーリーと関連する大きなダンジョンとサブコンテンツ的な小さなダンジョンの2種類が存在しており、それらをクリアしていく事で上限が増えていくような仕組みである。
ダンジョン内も本作のユニークなシステムを活かした攻略を促すようなものになっておりダンジョン攻略自体もモチベーションになるだろう。
また、物語を進めていけばコスト上限以外のカリモノに関する強化要素も用意されており、それもまた遊びの幅を広げる事に繋がり楽しさが増えていく。
それらの仕組みが前提である事からフィールド探索のモチベーションも維持しやすい。
カリモノにできるオブジェクトはフィールドやダンジョンに数多く落ちているうえ、倒した敵もカリモノにできる作りになっている。
そのため、フィールド探索のモチベーションも「カリモノ」がドリブンとなっており、ついつい新しいカリモノ探しをしてしまう楽しさがあるのだ。
更にカリモノ自体も様々な活用方法で遊びになるので、カリモノを手に入れた後の楽しさがあることもモチベーション維持の追い風になっている。
しかし、少し残念に感じるのは宝箱だろう。
多くの宝箱に入っているのがルピーだったりするのは少しガッカリ感が強い。
確かにルピーは余り頻繁にまとまった額を入手できないのだが、せっかく見つけた宝箱であれば可能な限り新しいカリモノや装備品の類が入っていて欲しい所だ。


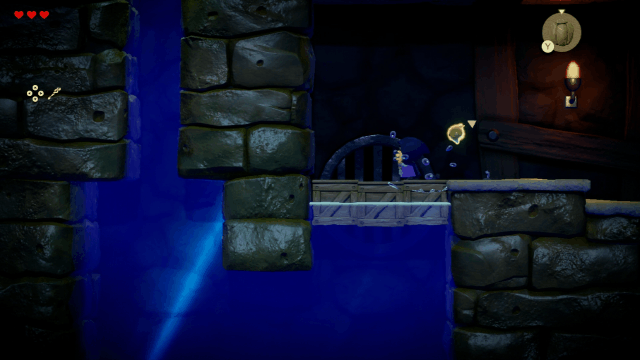
カリモノにはそれぞれに個性があり、単純にサイズの大きなもの、水の上に浮くもの、草や木箱に火を付けられるもの、隠れる事ができるものなど大量に用意されている。
召喚したオブジェクトもただ置くだけではなく、手に持ったり、押したりする事も可能であるため、そういった事ができる事も覚えておくと状況に応じて使い分ける事ができる。
また、図鑑を参照すると特殊な効果なども記載されているものがあり、そういった記載もカリモノの活用方法の参考になるだろう。
これらを駆使すれば本来ならば行けなさそうな場所も踏破できてしまうというプレイヤー毎に千差万別のプレイが行えることが最大の醍醐味だと言っても良いだろう。


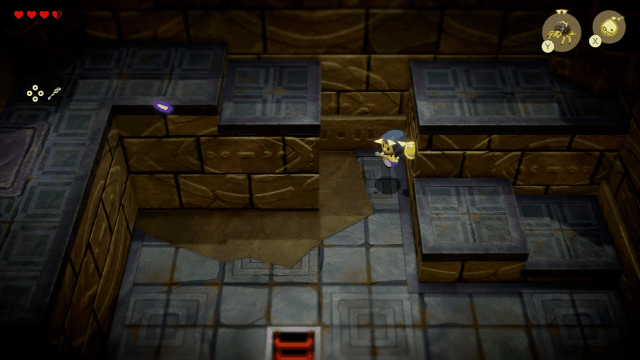
前述している通り、本作の主人公となるゼルダ姫は直接戦う手段に乏しい存在である。
ではどのように敵を倒すのかと言うと、こちらもまたカリモノを使用する。
投げつけられるアイテムを召喚する方法もあるが、倒した敵モンスターを召喚する事も可能なのだ。
これは普段は倒すだけになりがちなモンスターの力を借りて攻略できるというシチュエーション自体の特別な面白さも含まれており、「自分は直接戦わない」という少し狡猾でファジーな側面のある戦い方はイタズラをして遊んでいる時のような楽しさを生み出している。
召喚したモンスターは召喚直後にすぐさま攻撃行動を行ってくれるため、モンスターの種類によっては攻撃と再召喚を繰り返すと攻撃の回転率自体は良いだろう。
また、その場の地形なども考慮して、敵を遮りつつ、自分のモンスターだけが攻撃しやすいような状況を作るなど、咄嗟の機転による臨機応変な戦い方が出来た際には特に本作特有の楽しさを感じる事ができるハズだ。
召喚したモンスターは戦う事だけではなく、ダンジョン攻略などの地形踏破にも利用できる。
モンスターによっては滑空に利用できたり、よじ登りに利用できたりとモンスターの特性を理解すれば様々な方法での攻略が可能となる。
もしも、戦闘関連で追加して欲しい要素があるとすれば地形効果を出せるようなものが欲しい所だ。
例えば、足元の地形を水浸しにするカリモノを活用する事で電気関連の効果を行いやすかったり、地形の沼のようにできるカリモノによって踏破性を悪くさせ敵の機動力を低下させてハチの巣にしやすかったりといった要素をイメージしている。
必ずしも敵のリソースを直接奪うようなカリモノである必要は薄く、間接的に状況有利を作り出せるようなものが豊富にあっても新しい遊びが実現できたように思える。

カリモノ関連において問題となるのが召喚可能なオブジェクトの種類が増えてくると選択が非常に不便になってしまう点だろう。
自分で表示ラインナップをカスタムできるリストを作成したりといったオプションがあって然るべきであるように感じられる。
例えば、戦闘用リストと探索用リストを作成して、それぞれに普段使いしやすいカリモノを登録しておくことで戦闘時には戦闘用リストの中から有効なものを選択しやすくできただろう。
そこまで行かずとも、せめて使用頻度の低いカリモノを非表示化できたりといった要素が欲しい所だ。
カリモノはオブジェクトを召喚するような仕組みだが、別角度から表現すれば「全て異なる特性を持つアビリティー」の事でもある。
それが大量に存在する場合にアクセス性に問題が生じるのは容易に想像できたハズであり、なぜそこに対してのアプローチが何もなかったのかが不思議に思う所である。
なお、この問題はアップデートにより変更が加わったようだ。
「お気に入り」が設定できるようになり、お気に入りに設定したものだけを表示できるようなったので問題が少し解決できるようになった。
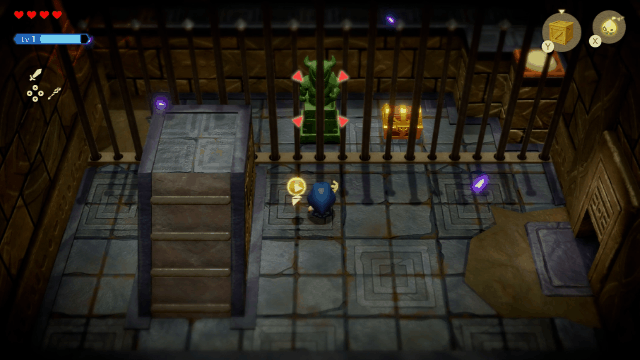
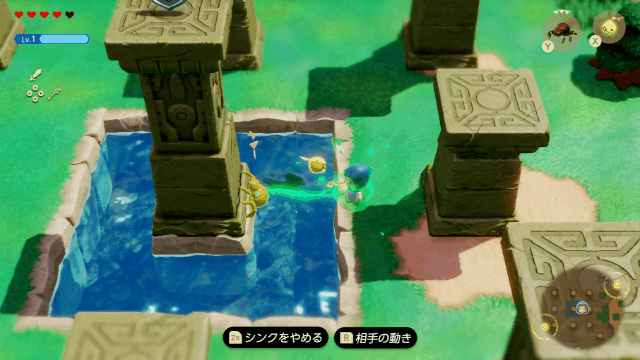
オブジェクトを召喚するだけでなく、オブジェクトの動作をトレースあるいはその逆が可能な「シンク」という機能も存在する。
どういうものかと言えば、移動するオブジェクトにシンクすればオブジェクトの移動と連動して自分が勝手に移動できる仕組みだ。
これを用いれば足場がない場所でも飛行しているモンスターにシンクする事で踏破する事も無理ではなくなるなど、使い方次第で無茶な攻略できてしまうと言う大胆な仕様である。
更にその逆である自身の動きにオブジェクトをトレースされる事も可能だ。
例えば、
他にも戦闘でも有効に活用可能で、召喚したモンスターが強くはあるものの動きが緩慢な場合、逆トレースをして自身の動きがモンスターと連動するようにすれば移動や回避をスムーズに行いつつモンスターに攻撃させるような事もできる。
こちらも発想次第でプレイヤー毎の様々な攻略が可能になっている。

カリモノ1つ1つは決して難解な機能は有していないが、それが何十個も存在して、それぞれに異なる特性が備わっている。
更にゼルダの使うシンクなどの機能も持ち入れば出来る事は掛け算的になってくる。
筆者がプレイした限りでは本作のボス敵を含めたダンジョン攻略の難易度が高いとは感じないが、この辺りの機能を忘れてしまうと途端に攻略方法に困ってしまう人はいるかも知れない。
特に非ダンジョンのフィールド探索程度であれば特定のカリモノだけを駆使して各地を踏破できるため、プレイヤーが獲得した機能(カリモノの特性など)を忘れてしまう可能性が高まってしまう。
日常的に固執して活用していたカリモノの機能がダンジョン内のややタイトな謎解きの場面になると通用せず、カリモノの特性とゼルダのアビリティーを活かしたような普段とは異なるアプローチをゲーム側が求めてくる。
そのため、普段から特定のカリモノばかりに頼らずに、色々なカリモノを試しながらプレイしていくとゲームプレイへの柔軟性が高まるだろう。

ここまでカリモノを駆使して攻略する側面を記述してきたが、ゼルダ姫本人に攻撃する手段が全くない訳ではない。
リンクの遺した剣の力を借りて剣士モードに変身する事ができる。
剣士モードになると攻撃が強力かつ連続で行えるようになるものの、ゲージを消費しながら発動するような形となるためここぞという場面で使うのが望ましい作りになっている。
あくまでもカリモノが主役であるバランスにしっかりとまとまっている印象だ。
グラフィック



ゼルダの伝説 夢をみる島のリメイク版路線の絵作りを採用したトップビュータイプのゼルダである。
ミニチュア的な可愛らしさがありつつ、ゲームとしての視認性と機能性が両立されたものになっている。
本作にはカリモノをどこでも召喚できるが、NPCの目の前でモンスターを召喚すると驚いたりするようなちょっとしたリアクションが用意されているのも嬉しい。
欲を言えば、召喚できるオブジェクトの種類も多いだけに、それに応じたリアクションパターンが多いとより嬉しかった。
サウンド
BGMはエリアによってシームレスに変化するようになっている。
フィールド曲はゼルダの子守歌のイントロから始まるなど、シリーズファンとしても「おぉ!」と思えるような楽曲になっているのではないだろうか。
総評
ゼルダの伝説 知恵のかりものはカリモノと言われるオブジェクトを召喚する事で実現される掛け算の遊びがプレイヤーのクリエイティブな思考を引き出す新機軸の2Dゼルダだ。
オブジェクトには様々な特性が設定されており、それらを組み合わせるなどして自分だけの攻略へと繋がるのが特徴的である。
特に地形などの状況を鑑みたオブジェクト召喚によって機転の利いた対処法ができた場合には本作固有の達成感が得られるのは大きな魅力だろう。
ただし、召喚可能なカリモノが増えてくると選択肢の中から目当てのものを探すのが大変になってしまう点は何かしらの調整が欲しかった。
外部記事
開発者に訊きました : ゼルダの伝説 知恵のかりもの|任天堂
『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』開発者インタビュー。主人公が戦闘中にベッドで寝てもいい。カリモノを使った“本物の冒険”はこうして生まれた | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com
【インタビュー】『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』外伝ではない。紛うことなき、王道の「ゼルダの伝説」 – Nintendo DREAM WEB
