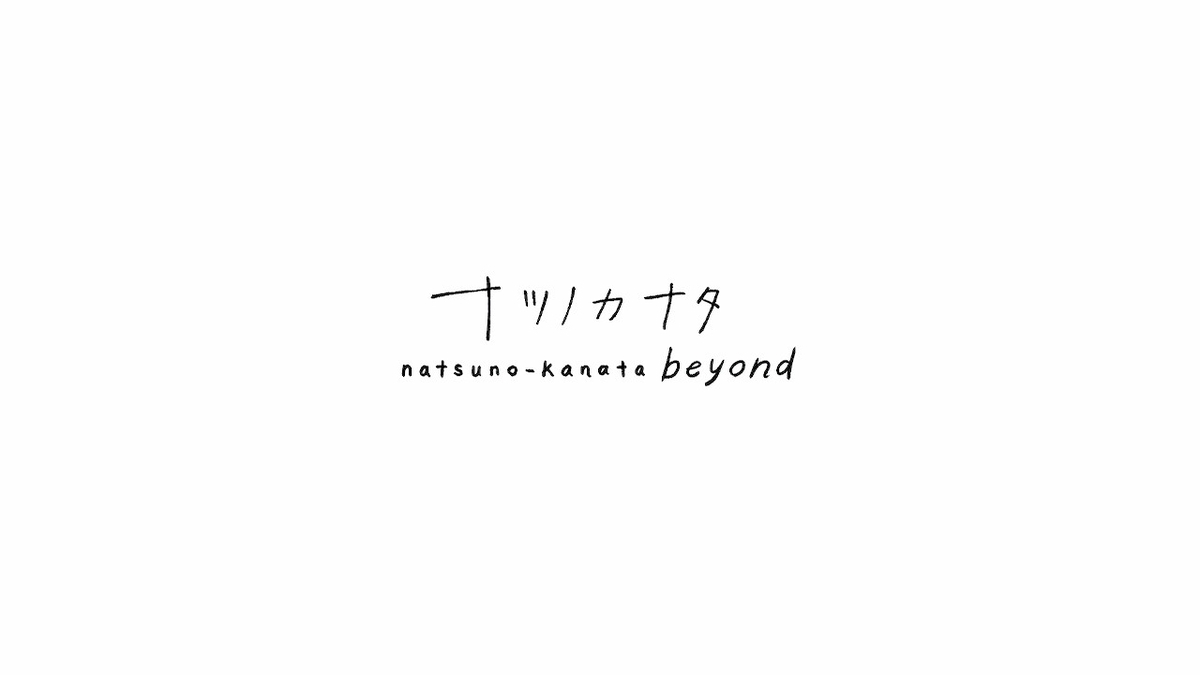
ナツノカナタ beyondは日本の個人開発者Kazuhide Oka氏が制作したテキストアドベンチャーだ。
本作は元々2022年にフリー版としてナツノカナタがリリースされており、それに追加要素などを加えて販売されたのがナツノカナタ beyondである。
筆者が本作を購入したいと思ったのはその設定である。
ポストアポカリプス的に退廃した世界で殺伐とし過ぎずにコミュニケーションを主体として進んでいくシチュエーションが魅力的に映ったのだ。
ストーリー

本作の世界は未知のウイルスによって世界的にアポカリプスに近い状態となったとされており、真夏の東京から離れるように北へと移動しているナツノというキャラクターと通話を通してインタラクションをする。
設定が非常に印象的であり、主人公は全く異なる別の世界からナツノとコンピュータを介して通話が可能になっている状態で、ナツノ側の状況は彼女のスマートフォンのカメラ越しにしかわからないというシチュエーションで進行していく。
ナツノと通話が行えている事もそうだが、物語を進める事で明らかに普通のウイルスによるものとは考え難い現象を目撃する事になる。
ナツノと一緒に旅を進めていく事でその謎が明らかとなっていき、それが物語としての興味を引く大きなポイントとなっている。
ナツノカナタの世界はポストアポカリプスへと向かっている最中の世界であり、人間の多くが亡くなるか、散り散りとなった寂れた世界の中で繰り広げられる日常的な会話のコントラストが魅力となっている。
もちろん、そんな世界になったからこその打ち明けられるシリアスな会話も多く、そちらもまたコントラストになっている。
また、本作の主人公には明確なバックボーンが設定されており、プレイヤーは主人公とは必ずしもイコールではない構図となっている。
そのため、物語を進めていくと主人公よりも通話先の相手であるナツノ達に共感しやすいのではないだろうか。
本作の物語では労働や教育が義務となった近代以降、配信やSNSが当たり前となった現代、COVID-19の流行により各国の都市がロックダウンした近年を生きる人と人との関わりの距離感の歪みと悩みが等身大に描かれている。
それを実存主義的な思考とSF的な設定を交えつつ独自の世界として表現しているのは見事だ。
物語としては広がった風呂敷を綺麗にたたむと言うよりもオープンエンドであり、それはテーマやメッセージ性ともマッチしているものになっている。
そのため、わかりやすい満足感のある結末というよりも、少しだけビターにも感じる読後感を覚えるものとなっている。

ナツノカナタ beyond版ではコマンドからキーワードを選択してナツノとのコミュニケーションを図るような方式である。
この仕組みは物語上で利用されることはもちろんだが、ゲームプレイ部分でも活用されるものとなっている。
なお、オリジナル版のような自分で入力する古来のADV作品的なプレイも可能である。


ストーリーを進行させていると一時的に同行する生存者キャラクターと出会うことがあり、そのキャラクターに関するサブストーリーへと発展する。
このキャラクター別のストーリーではキャラクター毎の様々な生き方と考え方、そして悩みがしっかりと感じられる内容になっており、本作の世界観とメッセージ性を支えるものになっている。
彼女達と出会う事で、その感性や苦悩に共感できる事も多いのではないだろうか。
システム

本作では探索パートがあり、ナツノに指示を出しながら色々な場所を探して回り食料などの物資を調達する必要がある。
中にはストーリーの進行に必要なアイテムが存在する事があるため、それを探索パートにて見つける事で物語が進行すると言うゲームサイクルでもある。
まとめると「ストーリー→探索→ストーリー→…」というシーケンスサイクルを想像するとイメージしやすいだろう。
探索はテキストベースとなっており「小さな部屋に着いたよ。ここには戸棚とアタッシュケースがあるね。」と言った報告を基にして何を調べて貰うかをコマンドによって指示するような形式となっている。
コマンドは「ストーリー」の項でも述べた通り、その場の会話や状況に合わせた適切なコマンドが表示・選択可能な状態になるが、こちらもマニュアルでテキストを入力する事も可能である。
また、何かしらの行動を行うとナツノが空腹にもなっていってしまうため、多く探索を行う場合には定期的に食事を取る事も大切だ。
探索を終えると別の探索エリアに継続して向かう事も出来るが、無事に帰る事が出来れば空腹状態は回復されるため、ある程度探索したら帰るというサイクル的なプレイとなるだろう。
更に探索中には敵に襲われることもあり、それを撃退するための装備品があると安心だ。
しかし、武器も使っていると壊れてしまうため、必須級のものではないが再び探索で調達した方が好ましい。
敵に襲われた際には体力が減ってしまうが、帰る事ができれば空腹状態と同様に回復する。
そのため、体力か空腹のどちらかが危険な状態であり、なおかつ回復する手段がないような場合には早期に帰る方が良いだろう。
ゲームとしての見た目としてはADV的であるが、これはローグライクをテキストアドベンチャー形式で行っているイメージを持つとピンと来やすいのかも知れない。
探索によって入手したアイテムは「クラフト」によって作り変える事が可能だ。
米を使っておにぎりを作ったり、木材と糸で釣竿を作成したりする事が出来る。
クラフトはそれなりにバリエーションも用意されている上に、料理関連に関しては回復量が大きくなるので持っていけば探索も捗りやすい。
このローグライトなゲームプレイ要素はオフにする事が可能で物語だけを読み進める事も可能となっているが、難易度として非常にシビアなものという事はなく、あくまでもストーリーや世界観を表現する手段として活用されている。
そして何よりもこの運要素の多いローグライトな作りであるという事も本作の物語のテーマともリンクしたものでありゲームプレイ体験と物語性をリンクさせている点も見事な作りである。

「ストーリー」の項でも述べたが進行すると生存者が仲間として増えることもある。
仲間となったキャラクターは探索が可能だが、探索を行ったキャラクターが空腹状態になっていくため、バランスよく探索させる事で長期間探索できるようにもなる。
探索中に行われる会話もキャラクター毎にしっかりと異なる。
また、独りで探索する事の多いナツノが他の人と活動・会話をしている姿も微笑ましく思える事だろう。
グラフィック



キャラクターの立ち絵イラストと背景が映像的なものとしては全てであり非常にミニマルではある。
キャラクターのイラストは温かく柔らかい雰囲気があり、背景は実写の写真をベースに加工を施したものを使用しているのが印象的だ。
サウンド
BGMは基本的に落ち着いた物悲しさのあるピアノと少し温かみのあるストリングスで構成されており荒廃した世界を会話をしながら旅するシチュエーションにマッチしている。
なお、BGMの一部はYouTube上でも公開されている。
筆者の好きになった楽曲もいくつか紹介しておきたい。
ノスタルジーを感じる「声を交えて」
優しく日常的な楽しさが表現された「常緑日和」
明るくもどこか寂しさを覚える「オーガンジーの景色」
キャラクターにはボイスはないが、欲を言えばフルボイスにまでなれば嬉しいところだった。
総評
ナツノカナタ beyondは現代的な人と人の関係性の機微を再認識させてくれる一作だ。
物語が伝えるメッセージ性とローグライトなゲームプレイはそのテーマに一貫性を有しており、オープンエンドなところがある締め方も読後感の余韻に心地よさを覚えるものである。
いつか、またこの夏の彼方へと戻り、変わらない彼女達と会話をして冒険をしたくなるだろう。
外部記事
ナツノカナタ original sound track - YouTube
少女との通話を通じて終末を迎えた異世界の謎に迫るノベルゲーム『ナツノカナタ beyond』Steam版が本日(6/20)発売。作者コメントも公開 | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com
Steam終末テキスト探索ADV『ナツノカナタ』正式リリース。高評価作品がついに正式版に、ついでになぜ完全無料なのか開発者に訊いた - AUTOMATON
“あー、楽しかった”だけで終わらない作品を作りたい―『ナツノカナタ』『午前五時にピアノを弾く』開発者・Kazuhide Oka氏インタビュー | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト